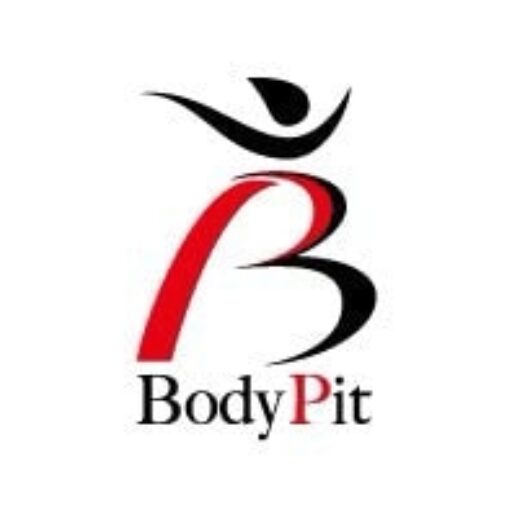野球肘とは
特に野球をプレイする少年や青年に多く見られる肘の障害の総称で、
主に投球動作が原因で発生します。 その痛みには内側、 外側、 後方の3種類があります。
■一般的に言われている原因
野球肘は、 過剰な投球動作や不適切なフォーム、 練習のしすぎなどが原因で肘関節に繰り
返しストレスがかかり、 以下の部位に障害を引き起こします。
・内側の痛み
肘の内側にある靭帯や筋肉が過度に引っ張られることで炎症が起きる。 最も一般的。
・外側の痛み
肘の外側の骨や軟骨が摩擦で損傷する。 成長期の子どもに多い。
・後方の痛み
肘を伸ばす際に後方部分にストレスがかかり、 炎症や痛みが生じる。
■症状
- 肘の内側または外側の痛み
- 投球時の不快感や鋭い痛み
- 肘の可動域制限
- 腫れや違和感
■一般的な治療法
・保存療法
- 安静: 投球を中止し、 肘を休める。
- アイシング: 炎症を抑えるために冷やす。
- リハビリ: 肘周辺の筋力を強化するためのエクササイズ。
・薬物療法
消炎鎮痛剤の使用(医師の指示に従う)
・手術
重症の場合、 靭帯再建術(トミー・ジョン手術)などが検討される。
■調律整体 坂本が考える野球肘について
今回は、ご相談の多い【野球肘】の内側症状についてお伝えしたいと思います。
そもそも野球肘とは、野球の投球動作を繰り返すことで肘に痛みが生じるスポーツ障害の総称です。よく見られる症状としては、高校生以上でしたら内側靭帯損傷、小中学生でしたら剥離(はくり)骨折が挙げられます。
一般的には、ボールの投げ過ぎや不適切なフォームが原因と考えられているため、球数制限を設けたり、整形外科などでもフォームチェックをしたり、といった対策が取られています。にもかかわらず、野球肘の症状を訴える人が減ったという印象はありません。
では、なぜ減らないのでしょうか?
・私の考える理由
私の考える理由は以下の3つです。
①足元の機能低下
②身体の感覚の低下
③形(フォーム)ばかりに囚われている
詳しく説明しますね。
①近年、便利・快適を求めて生活様式が大きく変化するに伴い、私たち人間の身体は弱くなっていると言えます。特に足元に関しては、靴の技術が発達するにつれて人間本来の足の機能を使わなくなり、足裏の感覚や足指を使うといった足元の機能の低下がみられます。
②私たちの全体重を支えて接地している足元が崩れているとなると、身体のバランス感覚の低下、身体の軸が弱いといった、全身への影響も出てきます。その状態でいくら練習をしても身体に余計な負荷がかかったり力みが出たりしてしまい、怪我につながるのです。
③有名なプロ野球選手のフォームを切り取ったSNSでの発信や指導法が見受けられます。それを見た子どもたちが表面的に取り入れ、その型にはまろうとします。しかし、根本的な身体の使い方までは真似できるはずもなく、見かけ上のフォーム重視になりがちです。その結果、やはり身体に負荷がかかって怪我につながってしまうのです。いかがでしょうか。思いあたることはありましたか?良かれと思っていた練習や努力が、知らず知らずの内に肘の内側に負担をかけ、内側の野球肘につながっている、ということがあるかもしれません。
■調律整体での治療法
ここからは、調律整体での治療法についてお伝えします。
まず身体を診させていただいて、どのような動きをしているのか、どこに負担をかけながら投げているのかを見定めます。身体は正直なので、筋肉の硬さや関節の動きを見るだけでも、その選手のクセが分かってきます。
次に痛めている箇所を施術していくのですが、肘が悪くなっている時は必ず肩の可動域と手首にも影響が出ます。この3関節の連動性を高め、神経と血液の流れを良くしていくと驚くほど回復が早くなります。
だいたい3ヶ月かかると言われている症状でも、1〜2回の施術で改善するケースがほとんどです。
そこから、投球フォームに大きな影響を及ぼす足元のケア、立ち方・歩き方のくせを治すための指導をし、フォーム作りをしていきます。
ただ痛みをとるだけではなく、再発しないようにする事、さらに怪我をする前よりパフォーマンスを上げる事まで視野に入れて施術をしております。
以上、今回は野球肘についてお伝えしました。
お読みいただきありがとうございました。